カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi
文学・歴史散歩 3 LITERATURE / HISTORY 3
3E
神奈川県・横浜 (司馬遼太郎「街道をゆく」から)
横浜・二俣川・鶴ヶ峰 (横浜市旭区)
鎌倉武士、畠山重忠の終焉の地である。畠山重忠とは、電子版広辞苑によると:
鎌倉前期の武将。源頼朝の臣。武蔵国畠山荘の人。荘司次郎と称。戦功多く、また徳望があった。北条時政に疑われ、北条義時に討たれた。(1164~1205)
横浜の鶴ヶ峰の麓二俣川古戦場は、畠山重忠が北条義時に討たれた地である。横浜市の西、私鉄の相模鉄道の鶴ヶ峰駅の西北、帷子川と二俣川が合流する横浜市旭区役所の辺りである。
司馬遼太郎は、『三浦半島記』(街道をゆく 第42巻)で「横浜・二俣川」を取り上げる。(平成7年(1995)の週刊朝日に掲載)
二俣川については、司馬は実際にこの地を歩いていないのではないかと思う。「街道をゆく」では彼が訪れた地は、豊かな風景描写があるが、そのような記述がない。
後述の貫達人の著作を参考にして書かれたと思われる。
横浜市旭区の地図
司馬は、この「横浜・二俣川」を書くにあたって、つぎのように記している。
重忠については、直接資料がないにひとしいため、学問的な方法での伝記が成り立ちにくい。その困難を押して書かれたのは、貫達人(ぬきたつと)著『畠山重忠』(吉川弘文館)である、と評価している。
その貫達人によると、重忠のことがわかるのは、『吾妻鏡』か『平家物語』『源平盛衰記』に書いてあるものがおもなもので、古文書のような良質な資料は一つも残っていないとのことである。その意味でたいへんな労作である。
畠山重忠は、平氏の滅亡期から鎌倉幕府の時代に生きた武将であった。
平家の滅亡
平家は、関東における土地争いなどにおいて、こまめに面倒を見る態度をうしなった。
このことについては、竹内理三は、ゆらぐ平家政権として、つぎのように書いている。
平氏から旧貴族や大神社が離反して孤立していっても、それだけなら平氏の軍事力でじゅうぶん相手を倒すことができた。平氏の真の孤立は、武士の棟梁として平氏に期待を寄せていた階層からも孤立したことであった。(竹内理三『武士の登場』(『日本の歴史』第6巻(中公文庫)から)
鎌倉幕府の成立
そこで関東において、平家に代わるべき武士の棟梁として頼朝が擁せられた。
坂東のひとびとが頼朝に期待したのは、統治者というよりも、関東の地で恒常的におこっている農地の所有をめぐる争いの裁(さば)き人(びと)としてであった。
司馬遼太郎は、中央の律令制(公家)に対して、じつに潔癖であった頼朝の政治的立場から説きお越し、好漢畠山重忠の生涯を見る。
◎1180年(治承四年)
重忠は、遅く頼朝に属した。頼朝がいまの房総半島にのがれて在地勢力の支持をうけた段階で、当時重忠は十七歳だった。頼朝の挙兵早々の段階では、重忠はこれを討滅すべき平家方に属した。父の重能(しげよし)が、当時、平家の武士として京都に在番していたためである。
◎頼朝は、自身が挙兵のとき重忠が敵方であったことが、奥歯の齲(むしば)のように感じていた。しかし、頼朝はその感情を越え重忠が好きであり、重用した。庇護者であった。頼朝は、北条時政(政子の父)の娘を重忠にめあわせ、相婿の間柄になった。
◎1184年(元歴元年)
『盛衰記』に登場する、義経の奇謀による鵯越(ひよどりごえ)の坂落としのなかで、重忠が馬をいたわり、それをかついで崖をおりたという話は有名ながら、このとき重忠は義経の陣中にはいなかったという。(貫達人)
◎重忠は、音感にすぐれ、器楽にも堪能であった。また、たいへんな力持ちであった。
◎1186年(文治二年)
義経没落後、その妾静(しずか)の 鶴岡八幡宮の舞では、銅拍子(どうびょうし)を打った。
◎1187年(文治三年)
重忠自身の罪ではなかったが、伊勢の沼田の地に派遣した代官が、御厨(みくりや)(伊勢神宮領)を侵した。代官の非は重忠の非であるとして囚人となる。表裏なく生きようとする者にとって、罪囚の身となったことはつらかった。食を断ち、眠らず、衰死しようとした。頼朝は、すぐさま罪を許し、重忠に感動した。
重忠は、衰弱した健康を回復させるためか、鎌倉から菅谷(埼玉県)の居館にもどった。梶原景時が、謀叛の疑いをかける。濡れ衣とわかり、頼朝の疑いは氷解した。後日、奥州征伐(1189年)では重忠のに先陣の名誉をあたえたりした。
◎重忠のには、つねにひかえめで、恩賞には淡泊で地位を得ようとしなかった。
好漢重忠、その声望の高さに妬心を持つ者がいた。
◎1199年(正治元年)
庇護者である頼朝は、五十三歳で没する。重忠三十六歳。
◎1203年(建仁三年)
北条の当主時政は、武蔵の大勢力比企氏を謀叛の疑いありとして討滅する。重忠は、幕府の召集であったため、討っ手に加わり勲功をたてた。(畠山氏は比企氏とともに武蔵における二代勢力だった。)
◎1205年(元久二年)
重忠が滅ぼされる。時政は、相模のみならず武蔵も自分の配下に置きたかったに違いない。
鎌倉で、にわかに動員令がくだされた。ひとびとは敵が何者であるかも知らずに駈けあわせるうちに、重忠の息子の重保が、由比ヶ浜で殺された。
その時期、重忠は、のどかに西進していた。いまの横浜市の旭区・保土ヶ谷区のあたりの二俣川まできて、一切を知った。
すでに眼前に数万の兵がみちみちている。かれらは、重忠に非違がないことを知っていたが、幕府の命によって寄手にまわったのである。
重忠はわずか百三十四騎ながらよく戦い、全滅した。
(重忠の事跡については、貫達人氏の著書に詳しい)
二俣川・鶴ヶ峰の古戦場を歩く
貫達人氏の著書『畠山重忠』の「十六 しのぶよすが」とともに歩く。
(貫氏は、鶴ヶ峰駅から古戦場を通り、薬王寺の六つ塚へ向かう。昭和37年かあるいはそれ以前のことと想像する)
≪鶴ヶ峰の古戦場である。横浜市旭区鶴ヶ峰本町にあり、現在、重忠の霊廟がある。俗に六つ塚という。六つ塚は、相模鉄道鶴ヶ峰駅の西北八百メートルあまり。≫
≪途中十二メートルあまりのかたびら川をわたる。いまはコンクリートの鎧橋、
むかしは鎧の渡し、あるいは矢箆淵(やのふち)とよんだところである。
この付近は重忠が戦死したところと伝える。≫
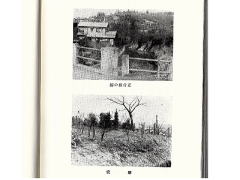
(上)鎧の渡付近 と (下)兜塚
貫達人氏著書写真(昭和37年頃?)
鎧橋の碑
平成15年に橋は撤去され、今はない。
現在の鎧の渡付近
川は埋め立てられ公園となっている≪川を渡って左方に小高い丘があり、上に小さな地蔵堂がある。重忠の兜を埋めたところといい、兜塚とよぶ。≫(上の左の写真の下)

現在の首塚(兜塚)
2013年春撮影カチアリキの知るところでは、この三十年程で、幾度かの河川改修があり、たいへんな様変わりであ る。蛇行していた流を直線に改修して、蛇行していた部分を埋め立てて公園、遊歩道、住宅地とした。したがって、貫達人氏の「鎧の渡付近」の面影はない。
兜塚も、今は住宅地の中にある。(左の写真)
≪六つ塚は六つ墓ともいう。松や竹などの林の間に、径五ー六尺、高さ二尺足らずの土饅頭が六つ散在する。重忠とその一族・郎従を埋めたところと伝える。附近最近住宅地にひらかれ小住宅が沢山たっている。≫

薬王寺の六ツ塚の案内

六ツ塚
貫達人氏は、二俣川の古戦場についてつぎのように書いている。「畠山(埼玉県大里郡川本町大字畠山で現在は深谷市)の方は道標もあり、遺蹟を大切にしようとする地元の誠意があらわれているが、鶴ヶ峰の方は、個人が掃除をしている程度らしく、あまり手が入っていない。それだけに、訪れるものに、しみじみとした感慨を抱かせるものがあり、低徊去る能わざる気持にさせられた。」と書いている。
貫達人氏が、古戦場を訪れてから半世紀が過ぎた。
旭区は区をあげて遺跡保存に力を入れて、道標・案内板を整備している。
畠山重忠を紹介する旭区のホームページも充実している。 ここ
貫達人「しのぶよすが」と
旭区のホームページの「旭区ふるさとの歴史再発見 鎌倉武将・畠山重忠」
を手に「古戦場」を歩いてみた。春の暖かい日、半日の歴史散歩であった。
参考文献・参考資料
司馬遼太郎『三浦半島記』(『街道をゆく』第42巻、朝日新聞社、1966)
貫達人『畠山重忠』(日本歴史学会編『人物叢書 新装版』、吉川弘文官、1974)
永井路子『畠山重忠公と二俣川・鶴ヶ峰』(横浜旭ロータリークラブ、1974)
*入手不能。横浜市立図書館中央館にある。
創和設計編;江本貴子挿絵『鎌倉武将 畠山重忠:旭区ふるさとのの歴史再発見 旭区誕生40周年記念改訂版』(旭区観光協会、2010)
**この冊子は、旭区のホームページで閲覧できるが、旭区役所1Fの総合案内所で頂ける。
竹内理三『武士の登場』(『日本の歴史』第6巻、中央公論社、1973)(中公文庫)
石井進『鎌倉幕府』(『日本の歴史』第7巻、中央公論社、1974)(中公文庫)
神奈川県・横浜
1/1